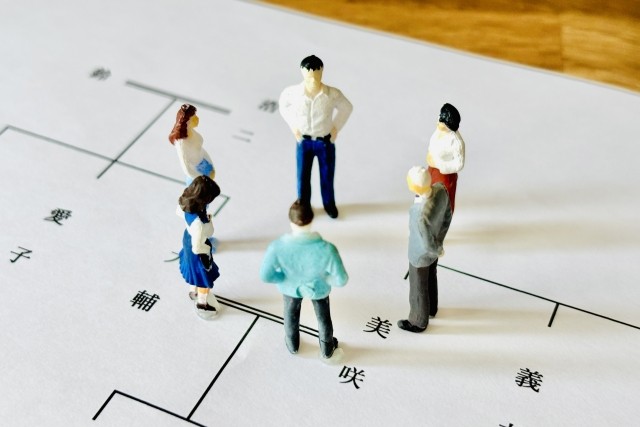相続人に認知症の疑いがある場合の成年後見制度利用ガイド
相続人に認知症の疑いがある場合の成年後見制度利用ガイド
「親が亡くなって相続手続きを進めようとしたら、相続人の一人である母が認知症のようで、遺産分割協議ができない…」このようなお悩みを抱えていませんか。
認知症により判断能力が低下した方が相続人に含まれる場合、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。この状況を解決するには、成年後見制度の利用が必要になります。しかし、制度の仕組みや手続きの流れがわからず、どこから手をつければよいか困っている方も多いでしょう。
この記事でわかること:
・成年後見制度の基礎知識と相続における必要性
・認知症の相続人がいる場合のトラブル事例
・成年後見人選任の具体的な手続きの流れ
・専門家に依頼するメリットと費用の目安
・今すぐ取るべき具体的なアクション
目次
1. 成年後見制度とは?相続における役割
成年後見制度の基本
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を法的に保護・支援する制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行います。
制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類がありますが、相続が発生してから必要になる場合は、通常「法定後見制度」を利用します。法定後見制度はさらに、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。
相続手続きにおける成年後見制度の必要性
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要な法律行為です。判断能力が不十分な相続人がいる場合、その方が行った遺産分割協議は法的に無効となってしまいます。
重要: 認知症の相続人を除外して遺産分割協議を進めたり、認知症の相続人に無理に署名・押印させたりすることは法的に認められません。後日、遺産分割協議自体が無効となるリスクがあります。
そのため、成年後見人を選任し、その後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。これにより、法的に有効な遺産分割協議を成立させることができるのです。
なぜこの制度が重要なのか
成年後見制度を利用することで、以下のメリットがあります:
- 法的に有効な遺産分割協議が可能になる
- 判断能力が不十分な相続人の権利が適切に保護される
- 不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きを完了できる
- 他の相続人が勝手に不利な内容で遺産分割を進めることを防げる
法定相続分で分ける場合は後見人不要?という誤解
「相続人全員が法定相続分で分けることに合意しているから、認知症の相続人がいても問題ない」と考える方がいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。
確かに法定相続分は法律で定められた公平な割合であり、誰にも不利益はありません。しかし、遺産分割協議は法律行為であり、その内容を理解し判断する能力が必要です。認知症などで判断能力が不十分な方は、たとえ法定相続分で分ける内容であっても、その「合意」自体ができないため、協議は無効となってしまいます。
注意: 「争いがないから」「本人に不利にならないから」という理由で、判断能力が不十分な相続人に署名・押印させることは、後日トラブルの原因となります。金融機関や法務局で手続きを拒否されたり、他の相続人から「無効だ」と主張されたりするリスクがあります。
遺産分割協議をせずに相続する方法も
ただし、1つの選択肢として、遺産分割協議を行わず、法定相続分のまま相続登記をする方法があります。この場合は成年後見制度を利用する必要がありません。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、不動産を「配偶者2分の1、子A4分の1、子B4分の1の共有」として登記することができます。この方法であれば、認知症の相続人の意思表示は不要です。
この方法のメリット:
- 成年後見人の選任が不要で、手続きが早い
- 後見人の継続的な報酬負担がない
- 法定相続分での登記は比較的シンプル
この方法のデメリット:
- 不動産が共有状態になり、後日の売却や活用に全員の同意が必要
- 認知症の相続人の持分を売却する場合、結局成年後見人が必要になる
- 預貯金の解約には各金融機関での複雑な手続きが必要
- 相続人の一人が亡くなると、さらに共有者が増えて権利関係が複雑化
どちらを選ぶべきか:
・不動産を今後売却する予定がある → 成年後見制度を利用して遺産分割する
・不動産を長期的に保有し、売却予定がない → 法定相続分での登記も選択肢
・預貯金が多額にある → 成年後見制度を利用した方がスムーズ
・将来的なトラブルを避けたい → 成年後見制度を利用して明確に分割する
いずれにしても、専門家に相談して、ご家族の状況に最適な方法を選択することをお勧めします。
2. よくある悩み・トラブル事例
ケース1:母の認知症に気づかず協議を進めてしまった
状況: 父が亡くなり、相続人は母と子ども3人の計4人。母は日常会話は問題ないものの、物忘れが激しく判断力に不安がありました。しかし、家族で話し合って遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印しました。
問題: 後日、法務局での不動産名義変更手続きの際に、母の判断能力について疑問を持たれ、医師の診断書の提出を求められました。診断の結果、母は中度の認知症と診断され、遺産分割協議時には判断能力がなかったことが判明。作成した遺産分割協議書は無効となり、手続きは振り出しに戻ってしまいました。
結果: 成年後見人の選任から手続きをやり直すことになり、余計な時間と費用がかかってしまいました。
ケース2:後見人選任を知らず相続手続きが進まない
状況: 兄が亡くなり、相続人は配偶者と母の2人。配偶者は相続手続きを進めようとしましたが、母が重度の認知症で施設に入所しており、全く意思疎通ができない状態でした。
問題: 配偶者は母と遺産分割協議ができないため、どうすればよいかわからず半年以上何もできない状況が続きました。その間、相続税の申告期限(10ヶ月)が近づき、焦りが募りました。
結果: 慌てて専門家に相談し、成年後見人選任の申立てを行いましたが、選任まで3ヶ月かかり、相続税申告は期限ギリギリとなってしまいました。
ケース3:親族間で対立が発生
状況: 父が亡くなり、相続人は認知症の母と子ども2人(長男と長女)。長男は「母の面倒を見てきたのだから自分が多く相続すべき」と主張し、長女は「平等に分けるべき」と反論。母は軽度の認知症で、長男の言いなりになってしまう状態でした。
問題: 長男は母を説得して自分に有利な内容の遺産分割協議書に署名させようとしましたが、長女が「母は判断能力がないのに無理に署名させている」と反発し、親族間で深刻な対立が生じました。
結果: 最終的に家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行い、第三者(専門家)が後見人に選任されました。客観的な立場の後見人により公平な遺産分割が実現しましたが、親族関係に大きな傷が残ってしまいました。
放置するとどうなるか:
・相続手続きが一切進まず、不動産や預貯金が凍結されたまま
・相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わず、延滞税が発生
・不動産の名義変更ができず、売却や活用ができない
・親族間のトラブルが深刻化し、関係が悪化
・判断能力が不十分な相続人が不利な条件で協議させられるリスク
3. 成年後見人選任の手続きの流れ
ステップ1:医師の診断書取得(約1〜2週間)
まず、認知症が疑われる相続人について、医師の診断を受け、診断書を取得します。家庭裁判所所定の診断書様式があるため、事前に裁判所から書式を入手しておくとスムーズです。かかりつけ医がいる場合はその医師に、いない場合は精神科や神経内科などの専門医に依頼します。
ステップ2:必要書類の準備(約1〜2週間)
申立てに必要な書類を収集します。戸籍謄本や住民票は役所で取得でき、登記されていないことの証明書は法務局で取得します。財産目録や収支状況報告書などは、本人の財産状況を正確に把握して作成する必要があります。
| 必要書類 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 申立書 | 家庭裁判所 | 裁判所の書式を使用 |
| 本人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内 |
| 本人の住民票または戸籍附票 | 住所地の市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内 |
| 後見人候補者の住民票 | 住所地の市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内 |
| 診断書(家裁所定書式) | 医療機関 | 作成から3ヶ月以内 |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局 | 本人について既に後見登記がされていないことの証明 |
| 本人の財産目録 | 自分で作成 | 不動産、預貯金、株式等のリスト |
| 本人の収支状況報告書 | 自分で作成 | 年金収入、医療費等の記載 |
| 不動産登記事項証明書 | 法務局 | 本人名義の不動産がある場合 |
| 預貯金通帳のコピー | 金融機関 | 残高がわかるページ |
ステップ3:家庭裁判所への申立て(即日)
準備した書類を本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。申立て時には収入印紙(800円)、登記印紙(2,600円)、郵便切手(裁判所により異なるが5,000円程度)が必要です。
ステップ4:家庭裁判所の調査(約1〜2ヶ月)
申立て後、家庭裁判所の調査官が本人や申立人、後見人候補者と面談を行います。本人の判断能力の程度、財産状況、後見人候補者の適格性などが調査されます。必要に応じて、本人の鑑定が行われることもあります(鑑定費用:5万円〜10万円程度)。
ステップ5:審判・後見人選任(調査完了後約2週間)
調査が終了すると、裁判所が審判を行い、後見人が選任されます。審判の結果は申立人と後見人に通知され、2週間の不服申立期間を経て、審判が確定します。
ステップ6:後見登記(審判確定後約2週間)
審判確定後、裁判所から法務局に後見登記の依頼が行われます。登記が完了すると、後見人は法務局で「登記事項証明書」を取得できるようになります。この証明書を使って、金融機関や法務局での手続きを行います。
ステップ7:遺産分割協議の実施
後見人が選任されたら、後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、後見人も相続人の一人である場合(例:子が親の後見人になっているケース)は、利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
全体の期間と費用の目安
期間: 申立て準備から後見人選任まで、通常3〜4ヶ月程度
費用:
・申立て費用:約1万円(印紙代、郵便切手代)
・診断書作成費用:5,000円〜1万円
・鑑定費用:5万円〜10万円(必要な場合のみ)
・専門家報酬(司法書士・弁護士):10万円〜20万円程度
・後見人の月額報酬:2万円〜6万円程度(財産額により異なる、継続的に必要)
4. 専門家のサポート内容
自分でやる場合と専門家に依頼する場合の比較
| 項目 | 自分で行う場合 | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 申立書類の作成 | 書式の理解や記載に時間がかかる。不備があると補正が必要 | 正確な書類を迅速に作成。不備による遅延リスクが少ない |
| 必要書類の収集 | どの書類が必要か調べる必要がある。複数の役所を回る手間 | 必要書類を一括して把握・取得。代理取得も可能 |
| 裁判所とのやり取り | 問い合わせや補正対応に不安。平日日中の対応が必要 | 書類作成や手続きのアドバイスでサポート。申立て代理は司法書士・弁護士と連携 |
| 遺産分割協議 | 法的に適切な内容か判断が難しい | 法的リスクを考慮した適切な協議内容を提案 |
| 期間 | 4〜6ヶ月程度(手続きに不慣れな場合) | 3〜4ヶ月程度(スムーズな進行) |
| 費用 | 実費のみ(約1〜3万円) | 実費+専門家報酬(合計15〜25万円程度) |
専門家に依頼するメリット
1. 時間と労力の大幅な削減
申立書類の作成、必要書類の収集、裁判所への提出など、複雑で時間のかかる作業を全て任せることができます。特に相続税の申告期限が迫っている場合、スピーディーな対応が可能です。
2. 法的リスクの回避
書類の不備や手続きのミスにより、申立てが却下されたり、遺産分割協議が無効になったりするリスクを避けられます。専門家は法的に適切な手続きを熟知しています。
3. 適切な後見人候補者の選定アドバイス
親族を後見人候補者とするか、専門家後見人を推薦するか、事案に応じた適切なアドバイスを受けられます。利益相反の問題など、トラブルを未然に防ぐことができます。
4. 相続手続き全体のサポート
成年後見人選任だけでなく、その後の遺産分割協議書の作成、不動産名義変更、相続税申告(税理士と連携)など、相続手続き全体をワンストップでサポートできます。
5. 精神的な負担の軽減
大切な家族が亡くなった後の手続きは、精神的にも大きな負担です。専門家に任せることで、手続きの不安から解放され、ご家族との時間を大切にできます。
当事務所でできること
当事務所では、成年後見制度を利用した相続手続きについて、以下のサポートを提供しています:
- 初回無料相談: 現在の状況をお聞きし、成年後見制度の利用が必要か、今後の手続きの流れを丁寧にご説明します
- 成年後見人選任申立書類の作成サポート: 家庭裁判所に提出する申立書、財産目録等の書類作成を支援します(※申立て代理は司法書士・弁護士の業務となります)
- 必要書類の収集代行: 戸籍謄本、住民票、登記事項証明書など、必要な書類の取得を代行します
- 家庭裁判所への同行サポート: 申立て時の裁判所への同行や、手続きのアドバイスを行います
- 遺産分割協議書の作成: 後見人選任後の遺産分割協議書を作成し、法的に適切な内容を提案します
- 相続手続き全般のサポート: 相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書作成など、相続手続き全体をサポートします
- 他士業との連携: 申立て代理が必要な場合は司法書士・弁護士と、相続税申告が必要な場合は税理士と連携してワンストップでサポートします
※行政書士は成年後見人選任申立ての代理はできませんが、申立書類の作成支援、必要書類の収集、手続きのアドバイスなど、申立て準備全般をサポートいたします。申立て代理が必要な場合は、連携する司法書士・弁護士をご紹介いたします。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 成年後見人は誰が選ばれるのですか?
A. 申立時に後見人候補者を記載できますが、最終的には家庭裁判所が選任します。本人の財産額が少なく、親族間に争いがない場合は、親族が選ばれることが多いです。一方、財産額が多い場合や親族間に対立がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれる傾向にあります。
Q2. 後見人になると、どのような義務がありますか?
A. 後見人は本人の財産を適切に管理し、本人の利益のために行動する義務があります。具体的には、財産目録の作成、定期的な収支報告書の家庭裁判所への提出、本人の生活費や医療費の支払い管理などを行います。また、本人の財産を後見人自身のために使用することは厳禁です。
Q3. 成年後見人の報酬はどのくらいかかりますか?
A. 後見人が親族の場合は無報酬とすることもできますが、専門家が後見人になる場合は月額2万円〜6万円程度の報酬が発生します。報酬額は本人の財産額に応じて家庭裁判所が決定します。例えば、財産が1,000万円以下なら月額2万円程度、1,000万円〜5,000万円なら月額3〜4万円程度が目安です。
Q4. 遺産分割が終わったら後見人は辞められますか?
A. いいえ、原則として辞められません。成年後見制度は本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで継続します。相続手続きのためだけに後見人を選任した場合でも、その後も後見人として本人の財産管理を続ける義務があります。これは制度利用前によく理解しておく必要があります。
Q5. 親族が後見人になった場合、利益相反とは何ですか?
A. 利益相反とは、後見人自身の利益と本人の利益が対立する状況です。例えば、子が親の後見人になっている場合、その親の相続では子も相続人の一人です。この場合、子が後見人として親に代わって遺産分割協議をすると、自分に有利な内容にできてしまうため、利益相反となります。この場合は特別代理人の選任が必要です。
Q6. 軽度の物忘れ程度でも成年後見制度が必要ですか?
A. 判断能力の程度によります。日常生活に支障がない程度の軽度の物忘れであれば、必ずしも必要ではありません。ただし、遺産分割協議の内容を理解し、その結果を認識できる程度の判断能力が必要です。心配な場合は、医師の診断を受けて客観的に判断することをお勧めします。
Q7. 法定相続分で分ける場合でも成年後見制度が必要ですか?
A. はい、必要です。これは多くの方が誤解しやすい重要なポイントです。「法定相続分で分けるのだから本人に不利にならない」「争いがないから大丈夫」と考えがちですが、法律的には判断能力が不十分な方が行った法律行為(遺産分割協議への参加)は無効となります。法定相続分で分ける内容であっても、その「合意」自体ができないためです。ただし、遺産分割協議を行わず、法定相続分のまま相続登記をする方法もあります。この場合は成年後見制度を利用せずに済むこともありますが、後日の不動産売却や活用に制約が生じるため、専門家に相談して判断することをお勧めします。
Q8. 相続税の申告期限が迫っています。間に合いますか?
A. 相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月です。成年後見人の選任には通常3〜4ヶ月かかるため、できるだけ早く手続きを始める必要があります。期限が迫っている場合は、すぐに専門家に相談してください。最速で進める方法をアドバイスします。なお、やむを得ない理由がある場合、税務署に申告期限の延長を申請できることもあります。
6. まとめ:今すぐ取るべきアクション
認知症の疑いがある相続人がいる場合、適切に対処しないと相続手続き全体が停滞してしまいます。以下のチェックリストを参考に、今すぐ行動を始めましょう。
今すぐ確認すべきこと
- 相続人の中に判断能力が不十分と思われる方がいるか確認する
- その方がかかりつけ医を持っているか、持っていない場合は専門医を探す
- 相続税の申告が必要か、必要な場合は申告期限を確認する
- 被相続人(亡くなった方)の財産の全体像を把握する
- 他の相続人と状況を共有し、協力体制を作る
1週間以内に行うべきこと
- 専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に無料相談の予約を入れる
- 医師に診察を依頼し、診断書の作成を依頼する
- 必要書類のリストを作成し、取得できるものから準備を始める
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所を確認する
専門家との相談時に準備すべき情報
- 家族関係図(相続人が誰か明確にする)
- 被相続人の財産の概要(不動産、預貯金、株式など)
- 判断能力が不十分な相続人の現在の状況(施設入所の有無、日常生活の様子など)
- 相続税申告の必要性と期限
- 親族間で意見の対立があるかどうか
行動の優先順位:
最優先: 専門家への相談予約(状況の整理と適切な手続きの確認)
優先: 医師の診断書取得(後見人選任の申立てに必須)
その後: 必要書類の収集、申立書の作成
※相続税の申告期限まで6ヶ月を切っている場合は、すぐに専門家に相談してください。
7. 無料相談のご案内
認知症の相続人がいる相続手続きは、当事務所にお任せください
当事務所では、成年後見制度を利用した相続手続きについて、初回無料相談を実施しています。
こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください:
- 相続人の一人が認知症で、どう進めればよいかわからない
- 成年後見制度について詳しく知りたい
- 手続きの期間や費用の見積もりが欲しい
- 相続税の申告期限が迫っていて焦っている
- 親族間で意見が対立していて困っている
ひろさわ行政書士事務所
〒501-0236
岐阜県瑞穂市本田1552-112
![]() 090-4084-1493
090-4084-1493
営業時間:平日 9:00 ~18:00
(土日祝日・夜間は事前予約制)
対応エリア:岐阜県、愛知県
※相談は完全予約制です。平日9:00〜18:00、土曜日も対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
あなたの相続手続きをスムーズに進めるために、全力でサポートいたします。